Japan Super Science Fairに参加した高校生を対象に、模擬講義および附属農場の見学ツアーを行いました(遺伝子工学研究室・森田准教授、果樹園芸学研究室・森本准教授)。 参加者:高校生・教員(45名):日本、オーストラリア、イギリス、シンガポールなど

2025年3月28日(金)午後、農学食科学部附属精華農場で「ACTR(京都府立大学地域貢献型特別研究)成果発表会」を実施し、京都府内の農業試験場や自治体、府立桂高校などから約20名の参加がありました。ACTRは、府内の市町村、企業、NPO等からの課題提案に対して府立大学教員が持つ特色ある知識を活かして共同研究を行い、府内の地域振興や産業・文化の発展等に貢献する目的で実施しています。
本学科の教員から研究成果の報告が行われ、資源植物学研究室の板井教授からAIやドローン等を活用した鳥獣害対策へのスマート農業、並びに、京都在来ブドウ品種「聚楽」の復活に向けた取組み、遺伝子工学研究室の森田准教授から宇治茶の収量・品質予測、野菜花卉園芸学研究室の伊達講師から「洛いも」(ダイショ)の新たな利用方法に関する研究紹介がありました。発表内容に関して、高校生を含む参加者から様々な質問がありました。
京都府立大学地域貢献型特別研究(ACTR)
地域貢献型特別研究(府大ACTR)
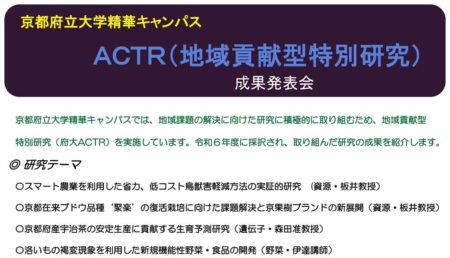
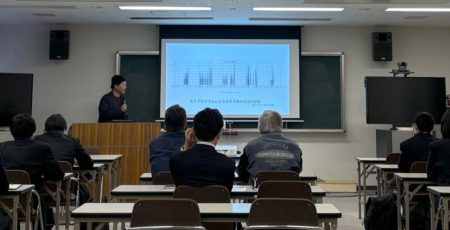


京都府農林水産技術センター(府の農業研究所)-府立大学-農林水産系高校等と実施している「農林水産技術交流会」が、2024年9月26日(木)、府立農芸高校で開催されました。
府立大学からは農学生命科学科を含む教員・学生が参加し、ポスター発表を行いました。画像は、本学科・果樹園芸学研究室の学生のポスター発表に耳を傾けている農芸高校の湯川校長先生です。

その後、農芸高校の田や温室、牛舎などの施設を見学しました。画像は、シクラメンを栽培中のガラス温室です。

2月17日に、卒業論文発表会を開催しました。
3年ぶりの対面開催ということで、本学科4回生が卒業研究について発表しました。
質疑応答にもしっかり対応しており、成長を感じさせてくれました。
皆さん、お疲れ様でした!
2022年6月に設立された「未来食研究開発センター」の記事が日経バイオテクに掲載されました。
https://bio.nikkeibp.co.jp/atcl/news/p1/22/12/05/10221/
「未来食研究開発センター」は、本学科の増村教授(副学長、遺伝子工学研究室)と、武田准教授(細胞工学研究室)が2022年6月に設立した、府大発のスタートアップ企業です。現在、矮性イネ、自然栽培、食用昆虫に関する事業を進めています。
京都府立大学の学園祭「流木祭(なからぎさい)」に合わせて、府大生による学科紹介や大学施設を案内するキャンパスツアーを開催しました。
農学生命科学科の現役生2名が、来てくれた高校生30名を案内しました。
ご参加いただいた高校生の皆様、ありがとうございました!

ツアー受付

光る植物(植物育種研究室)

エミュー(大きくなったなぁ・・・)
京都府立桂高等学校(京都府京都市)の研究提案「懸崖菊優良品種の茎頂培養による保全と重イオンビームによる新品種の育成」が、バイテク情報普及会が主催する「第6回 高校生科学教育大賞」で最優秀賞を受賞しました。
https://cbijapan.com/education/
「高校生科学教育大賞」は、これからを担う高校生が「植物バイオテクノロジー」と「持続可能な農業」とについてより深く学び考えるきっかけつくることを目的に2017年に設立され、毎年支援対象校を公募しているものです。上記の研究提案では、本学科の野菜花卉園芸学研究室卒業生の宮脇潤先生が関わり、高校での教科、TAFS(課題研究:第2研究群、教員3名、生徒38名)の授業において、植物バイオテクノロジーの技術を利用して、京都の伝統的な在来品種や栽培方法の保存、地域の農業振興などにも貢献されています。今回は3名の生徒が研究提案を行い、京都府向日市の特産品である懸崖菊(けんがいぎく)の生産農家が1軒だけになった状況をバイオテクノロジー技術で救おうとする着想が高く評価され、受賞に繋がりました。
この研究では、重イオンビーム照射を理化学研究所 仁科加速器科学研究センター 生物照射チームが、植物組織培養技術を本学科の植物育種学研究室がサポートしています。

<参考>
・京都府立桂高等学校
http://www.kyoto-be.ne.jp/katsura-hs/mt/
・理化学研究所 仁科加速器科学研究センター 生物照射チーム
https://www.nishina.riken.jp/labo/muta_bio.html
・農学生命科学科 植物育種学研究室
・農学生命科学科 野菜花卉園芸学研究室
https://eureka.kpu.ac.jp/~takaaki/
2回生の下鴨農場実習の特別編です.京都府立農芸高校にお世話になって,畜産関連の実習を行ってもらいました.
5つの班に分かれて5種類の実習をしました(1搾乳,2和牛体重測定,3和牛ブラッシングと餌やり,4農場HACCP認証鶏舎での採卵,5牛の卵子・精液観察).
今回の写真は,養鶏場の衛生管理の方法と餌を変えて白い君の卵を生産しているところを教えてもらっているところと和牛の体側をしているところです.幸紀夫の胸囲をはかっているところです.
学生の感想より:乳牛は丸々と肥っているイメージだったが,実際に近くで見ると背中の骨がくっきりと見えていたので驚いた.搾乳器をつけるまでに,牛乳に汚れが入らないように多くの工程があって,かなりしっかりと品質管理されていることが分かった.28ヶ月の牛は向こう側が見えなくて大きな壁の様に感じました.牛舎にいた乳牛は牛の腰周り骨格がゴツゴツしていて肉牛とは全然違いました.話を聞いてみると,乳牛は産道を大きくしたり乳房を沢山支えるために骨盤が発達しているということがわかりました.全ての牛にクレインという草の餌と成長期の牛には栄養がたっぷりあるとうもろこしや大豆,小麦を混ぜた餌をあげました.牛は栄養のある餌の方が好きみたいで,そちらばかり食べていました.牛の卵巣は人間よりもとても大きいイメージだったのですが、スーパーボールほどのサイズで驚きました。続いて液体窒素に入れて保存されていた精液を牛の体温と同じ38℃のお湯で融解.お湯につけた瞬間活発に動き出した様子を顕微鏡でみて感動しました.HACCP認定鶏舎では,菌を持ち込まないようにする取り組みや,誰が作業しても水準を保てるような取り組みを学んだ.白い卵の話が興味深かった.白いオムライスやアイスをぜひ食べてみたいと思った!





地域貢献型特別研究(ACTR)では、香りや有機酸など果実成分の分析、食品機能性の評価に取り組んでいます。